オーストラリアのデザイン学者、キーズ・ドルスト(Kees Dorst)は、著書「Frame Innovation」の中で、デザインによる創造性の思考法、理論を展開しています。
イノベーションを起こす上で、重要な考え方が、思考の枠組みそのもの(フレーム)にイノベーションを起こすことだという考え方に基づいています。
2015年にMIT Pressから出ている本ですが、英語版しか出回っていないこともあり、その学術的・実務的な貢献もさることながら、日本ではあまり流通していない考え方になってしまっているようで、こちらで紹介させていただきます。
※この記事では、Kees Dorst氏をカタカナ語表記で、「キーズ・ドルスト」と表記しましたが、2020年6月現在、日本語での表記が定まっていないようで、数ヶ月前にgoogle検索した際には、「キーズ・ドースト」と約表記されていました。そしてキーズ・ドーストで検索すると、「チーズ・トースト」が予測変換されるなど、Kees Dorst先生の知名度がまだまだ低いことを物語っているように思います。。。
目次
背景:「デザイン思考」の人気
これだけデザインがイノベーションや経営にとって重要なテーマとして考えられている時代もありません。背景として、いわゆる「デザイン思考」が人気を博していることがあります。Dorstの論文を見てみましょう。
In the last few years, “Design Thinking” has gained popularity e it is now seen as an exciting new paradigm for dealing with problems in sectors as far a field as IT, Business, Education and Medicine. This potential success challenges the design research community to provide unambiguous answers to two key questions: “What is the core ofDesign Thinking?” and “What could it bring to practitioners and organisations in other fields?”.(Dorst,2011)
2011年の論文、「The core of ‘design thinking’ and its application」の中で、Dorstは上のように述べています。要約すれば、次のような問題意識があります。
- ここ数年、「デザイン思考」は人気を博し、問題に対処するためのエキサイティングな新しいパラダイムと見なされている。
- この潜在的な成功は、デザイン研究のコミュニティに、2つの重要な質問に対する明確な答えを提供することに挑戦している。
- 「デザイン思考の核となるものは何か」
- 「他の分野の実務家や組織に何をもたらすことができるのか」
フレーム・クリエーション:「デザインプラクティスのコア」
結論を先に言えば、「デザイン思考」のコアは、「フレーム・クリエーション」だという説をDorstは唱えています。
では、そもそもFraming(フレーミング)とは何でしょうか?
‘Framing’ is a term commonly used within design literature (since (schön, 1983)) for the creation of a (novel) standpoint from which a problematic situation can be tackled. Although frames are often paraphrased by a simple metaphor, they are in fact very complex sets of statements that include the specific perception of a problem situation, the (implicit) adoption of certain concepts to describe the situation, a ‘working principle’ that underpins a solution and the key thesis.(Dorst, 2011)
一言で表してみましょう。
フレーミングとは、問題のある状況に対処するための(斬新な)立場(Standpoint)を作り出すことである.
そのための思考方法を明らかにしたのが、本書です。
デザイン学界隈での評価
デザイン学のコミュニティでは、近年のデザイン理論の著書の中では、デザイン学の基礎的な考え方への高い貢献として高く評価されています。
デザイン学の理論というと、そのものの考え方自体に議論が多いのが実情ですが、そんな中でも、本書は、基礎理論への貢献として評価が高いです。
>関連記事

私の通うミラノ工科大学でも、デザイン学部と経営学部の両方の教授陣からも高い評価があります。推薦者の一人に、ミラノ工科大学のロベルト・ベルガンティ先生もいます。デザイン学を学ぶ人はもちろん、デザインを通じてイノベーションを検討したいという実務家にとっては、必読書の一冊です。
Ciao, grazie!
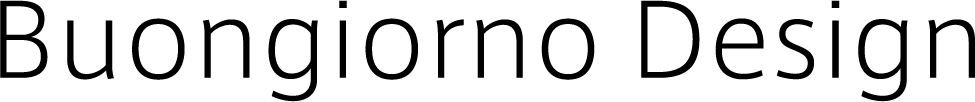



コメント