大学の研究・教育活動では、「授業設計」ということが求められます。
博士課程のコースでは、「教育戦略」というような授業があるくらい、重要な取り組みです。「Teaching Strategies, methods and styles」という授業で、大学教育の戦略・方法、スタイルを体系的に学びます。
実際に、授業を設計する、とは、どのようなことなのでしょうか?
今回、講義を実際に設計して、実施させていただける機会に恵まれましたので、その時に気をつけたことなどを書いてみたいと思います。
講義は、インドのデザインスクールでデザイン・ドリブン・イノベーションのワークショップの企画をしました。
修士時代のインド人の友人からのお誘いがあって、また一緒にこうして仕事ができることが、何よりも嬉しく、人生の喜びでもあります。
目次
デザイン・ドリブン・イノベーションのWS
今回の企画は、インドで伝統ある大学のマスターコースでの講義というものでした。
デザイン・マネジメントに特化したコースの中で、少し新しい取り組みを取り入れたいと教授陣は考えているようです。
これまで、米国を中心としたユーザー中心の問題解決型アプローチを積極的に取り入れてきましたが、新たに、イタリアを中心に欧州に伝統が深いデザイン・ドリブン・イノベーション(以下DDI)のアプローチをマスターコースに取り入れていきたい、と大学で検討しているようでした。
そこで、ミラノ工科大学のアプローチを参考にしつつ、まずは実験的に取り入れてみよう、という研究・教育の取り組みの第一歩としようというのが今回の活動の位置づけでした。
3日間の集中WSの設計
DDIを取り入れる最初の取り組みであることから、まずは試験的に3日間程度のワークショップを実施したいとのことでした。
3日間でDDIのすべてをマスターするには、時間的にも分量的にも厳しいですが、そのエッセンスだけでもぎゅーっと絞って、学生向けにWSを実施したい、という教授の熱い思いに共感し、無理は承知で計画を立ててみることになりました。
教育カリキュラムとしてのWS設計
今回のWSの設計で肝となるのが、教育カリキュラムである修士コースでのWS設計ということです。
教育戦略としては、教育側が一方的に知識を伝授する講義中心のものというよりも、学生が主体性を持って学ぶことができる、いわゆるアクティブ・ラーニングのアプローチを導入することにしました。
さらに、コロナ禍の中での遠隔授業の設計ということで、どのように評価し、モチベーションを上げてもらうかということは、とても重要で、チャレンジとなりました。
ILOsの設計
アクティブ・ラーニングの設計で、最も重要な考え方は、学生中心の学習体験設計です。
とりわけ、最も重要なのは、ILOs(Intended Learning Outcomes: 意図された学習結果)の計画です。専門的な言葉で聞き慣れないですが、要するに、何を学んでほしいか、ということ、ゴールです。
何を学んでほしいかが明確でなければ、学生にとってはその学習時間は効率が悪いし、場合によっては無駄になってしまいます。しかも、大学での他のカリキュラムとのバランスを考えて、補完しあえるような内容に計画することがベストです。
今回は、明確に、「DDIのと戦略的デザインの導入」に的を絞った計画としました。

アクティブ・ラーニングを設計する際の3つの柱
関連記事

評価システムの設計
評価システムの設計も極めて重要です。何しろこの基準によって、学生の成績評価がついてしまうのですから、責任重大となります。
教育陣で話し合って講義内容の理解度やプレゼンのストーリー、プレゼン内容の充実度などの観点を取り入れながら、学習が十分になされたか、ということを総合的に見ていこうときめました。
モチベーションシステム
3日間という中で成果を確実に出してもらうためには、モチベーションを高めてもらうことが必要です。
聞いてみると、クライアント向けのコンサルティング課題という形式の講義はこれまでにこのコースの中では実施したことがない、ということでした。そこから、卒業後、プロフェッショナルとして働いていくため、できるだけ実務に近いイメージでの講義にしてはどうか、という話になりました。
インドの大手飲料メーカーを仮想クライアントとして想定し、彼らの抱える経営−デザイン課題に対してソリューションを提案する、という形式にしました。
教育メンバーは、クライアント企業の担当マネージャーという設定とし、レビュー時には毎回プロフェッショナルな対応が求められる、という状況設定としました。
さて、本番がどうなるか、とてもワクワクドキドキしますね。
Ciao! Grazie!
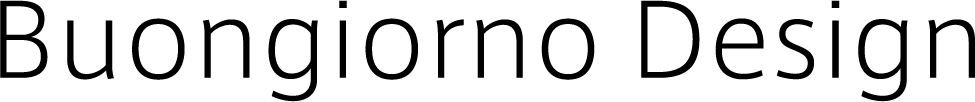
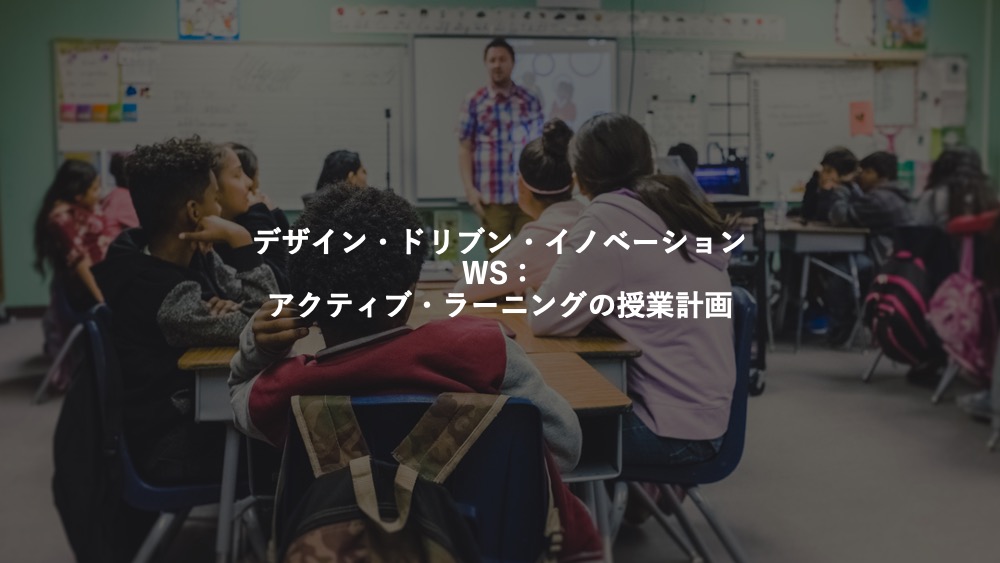


コメント